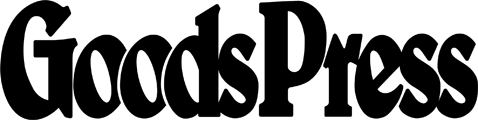ーー自動車メーカーがニュルでの車両開発を本格化させたのは、ここ20年ほどのようですが、日産自動車ではどなたが最初に、ニュルでのテストを提案されたのですか?
加藤:その話をする前に、まずはクルマの歴史をたどる必要があるかもしれませんね。スカイラインといえば、“ハコスカ”、“ケンメリ”という3世代目、4世代目のモデルが数々の伝説を残しました。しかし、“ジャパン”という愛称で呼ばれた5世代目のC210辺りから、その神通力が通じなくなりつつあったのは事実です。R31の開発責任者は、当初、かの有名な櫻井 眞一郎(※1)さんでしたが、体調を崩され、途中で櫻井さんの右腕だった伊藤修令(※2)さんにバトンタッチされたのです。

“ハコスカ” スカイライン GT-R(KPGC10)

“ケンメリ” スカイライン GT-R(KPGC110)

“ジャパン” スカイライン(C210)
※1/櫻井 眞一郎(さくらい・しんいちろう) 1929年、神奈川県生まれ。横浜国立大学機会工学部卒業後、清水建設を経て1952年に、たま自動車へ入社。たま自動車は後に、プリンス自動車工業へと改称し、1966年に日産自動車と合併。1957年に発売された初代スカイラインから設計を担当、以降、2世代目のS50系から6世代目R30までスカイラインの開発責任者を務める。7世代目のR31開発中に病に倒れ、開発責任者の役目を右腕の伊藤修令氏に引き継ぐ。病からの回復後、オーテックジャパンの初代社長に就任したほか、スカイラインミュージアムの館長に就任するなど、精力的に活動を続けた。2011年、死去
※2/伊藤修令(いとう・ながのり) 1937年、広島県生まれ。広島大学工学部卒業後、プリンス自動車に入社。初代スカイラインのほか「ローレル」や「マーチ」など、幅広いクルマの開発を担当。桜井 眞一郎氏の後を受け、7世代目R31スカイラインの開発末期から開発責任者となる。8世代目R32スカイラインでも開発責任者を務め、GT-R復活を指揮した。後にオーテックジャパンの常務取締役、日産自動車のモータースポーツ部門であるニスモのテクニカルアドバイザー、オーテックジャパンの顧問などを歴任

“7th” スカイライン(R31)
R31スカイラインは、ローレルとシャーシモノコックを共有していて、トヨタの「マークII」を追いかけていました。ローレルと同じシャーシを使うことでクルマも大きくなっていましたし、セールス的にも伸びなかった。
伊藤さんは、スカイラインの没落が許せなかったみたいです。常々「スカイラインの根底にあるのは走りだ」とおっしゃっていました。そこで、次のR32は「まずFR(後輪駆動)で100点のクルマを作れ!」と指示されたのです。モノコック、エンジンはもちろん、マルチリンク式のサスペンションなど、新しい技術・機構を随所に導入。そして、その仮想ターゲットは、当時、完成度の高いFRスポーツカーとして評価を得ていた、ポルシェの「944」でした。

スカイライン(R32)
ですが、伊藤さんの頭の中には「スカイラインを復活させるには、より高性能なGT-Rの存在が必要だ」という考えがあったようです。私たちにも詳細は知らされていなかったのですが、“GT-X計画”、つまり、GT-Rの開発が、早期からスタートしていました。そもそも、FRで100点なんですよ。それよりハイパワーで、高度なシステムなクルマを組むとなると、100点の枠には収まらないでしょう(笑)。
そこで、当時の開発メンバーの間で「そのクルマをどこで開発するのか?」という話になり、「じゃあ、ドイツだ!」となったのです。なぜドイツになったかといえば、ポルシェやメルセデス・ベンツの本拠地がある国だし、速度無制限のアウトバーンがある国だから、という理由です。その頃、実験の主担だった渡邉衡三(※3)さんはニュルをご存じでしたので「では、ニュルに行こう!」と決まったようです。
※3/渡邉衡三(わたなべ・こうぞう) 1942年、大阪府生まれ。東京大学 工学部 修士課程終了後、1967年に日産自動車へ入社。「スカイライン」、レース車両のシャーシ設計などを経て、本社開発本部へと異動。後に、車両実験部に配属となり、R32の実験主任を担当。その後、R33、R34スカイラインの開発責任者を務める。1999年に取締役としてニスモへと出向。2006年に引退