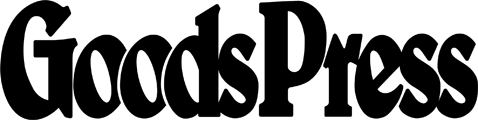■“マジョリティとマイノリティの二律背反”を体現する足元
【お気に入りの1足】
NIKE
「AIR VORTEX」

▲映像ディレクター・畔柳恵輔さん(37歳)
個人でもクリエティブを世界に発信できる現代においてなお、一部の才能ある人々にのみ許された世界というイメージの強い“映像業界”。そこに畔柳さんが足を踏み入れたのが2008年。「中学生の頃に映像の世界に出会い、武蔵野美術大学・映像学科を卒業し、新卒で〈電通テック(現・電通クリエーティブX)〉という広告制作会社に入社。その中のテレビCM制作・演出の部署に在籍しました」。業界の人間ならば知らぬ者のいない超実力派クリエイターらを輩出してきた同部署。そこでキャリアを積んでいくも社内指名は無く、貼られたのは“くすぶり”のレッテル。だが入社6年目、遂に転機が訪れる。とある広告賞を受賞したのだ。
「すると会社の僕への態度がハッキリと変わって。今思えば、それも自分の成長に必要なステップだったんですが、当時は天邪鬼の塊だったので、『今まで周りに想いが届かなかったのに、賞を1つ取っただけでみんな俺のいうことを聞くのかよ!』と憤りにも近い戸惑いを感じて…そこで吹っ切れました。それに広告の世界は自分の好きを貫くだけではやっていけない部分もあり、自分が好きで入った世界を嫌いになるのが怖くなって、退職を決意したんです」。
周囲には揶揄する人、心配してくれる人とさまざまだったが、その全てが面倒臭くなった彼は、日本を離れ一路、“微笑みの国”タイへと飛んだ。


両親の生まれは根津と向島、自身も東京生まれ・東京育ち。そんな生粋の江戸っ子が、右も左も分からぬ国で「アイム ア フィルムディレクター」という自己紹介だけを武器に、アジア、アメリカ、ヨーロッパを巡った計240日間。まさに29歳・アラサーの大冒険。とはいえ、ただ遊びに行ったわけではない。そこで自分自身のルーティーンとして、1日1本1分間の“今、僕がいる場所で見た景色”を定点観測的に撮り続け、SNSにアップしていた。
「それを見て、僕のことを面白いと感じてくれていた人たちが、ありがたいことに声をかけてくれて、2015年10月にフリーランスの映像ディレクターとしてデビューしました」。そして現在、フリーランス歴も7年目。これまでを振り返り、改めて自分自身の原点について考えることも。「“こういうモノが好きで、こういうモノを栄養に育ってきたんですよ”という自己のキャラアピール期を経て、次にそれを恥ずかしいと感じる時期も過ぎ、今はここまで自分を形成してきた要素がクリエイティブに自ずと滲み出てくるのを楽しめる。そんなフェーズにきたと感じています」。


祖父母との思い出が詰まった父の生家の1階。これまで買い集めてきた膨大な映画・音楽関連の雑誌や書籍、国民的ビッグタイトルからニッチな作品まで網羅したマンガにDVD、さらにアメリカントイに古着、スニーカーが雑多に積み重なった部屋の真ん中で彼は話を続ける。…そして今も自身の創作の根幹にある、とある人物の言葉について触れた。
「美大時代、アニメ監督の大畑晃一さんが客員講義でいらっしゃった際に、『B級が大好きなんです』とドヤ顔で言い放った僕に対し、笑いながらこう返してきたんです。『いいか、メインストリームを熟知している人間だけが、サブカルチャーを愛しています! といえるってことを忘れるなよ』と。すごくハッとさせられたのを覚えています」。その言葉は、のちのスタンスにも大きな影響を与えた。
若い頃は自分の個性をいかに表現するかに腐心していたが、映像業界でメンコの数を重ねるうちに、ディレクターとは一般的な社会と専門的な世界を橋渡しする役割を担う。ゆえにその相反する2つの視点を持つことが何よりも重要なのだと知った。「要は、クライアントからの課題や受け手側のニーズに対して、いかに自分のクリエイティビティを反映しつつ応えられるかということです」。こうして有名企業のCM、国民的アイドルグループのMV、ドラマやドキュメンタリーまで、彼の生み出す作品に見られる“マジョリティとマイノリティの優れた二律背反的バランス感覚”は養われていったのである。さて、ここらで本題となるスニーカーについて。

クリエイターと呼ばれる人種、それも世のトレンドの最先端をいく“映像の世界”の人々の足元には、レアリティの高いハイプなスニーカーが履かれている。そんな筆者の思い込みはすぐに打ち砕かれた。畔柳さんが履いていたのは、玄人好みなナイキのレトロランニングモデル「AIR VORTEX」。それもブルーのスウェード素材と、ホワイトのナイロン生地×メッシュ生地のコンビアッパーに、ゴールドカラーのスウッシュが光る王道配色。しかし、仕様か自身のエイジングによるものか、何ともイイ感じにヤレている…いやヤレまくった風貌は、世間の声にも左右されぬ揺るぎなき自身のスタイルを体現しているとも読み取れる。
「たしか大学生時代の終わりの頃か、社会人になってすぐの頃に買いました。その昔、ハイテクなデザインを指す形容詞として“ウルトラマンぽい”ってあったじゃないですか。これもスウッシュからヒールタブへと繋がるゴールドがなんとなくスペーシーで、僕の中の天邪鬼な部分と目立ちたいゴコロを刺激しました。また、メイド・イン・USAのアイテムをどこかに必ず入れたいというマイルールもクリアしつつ、ナイキを履いていることで自分の中のオシャレ満腹中枢をも満たしてくれます(笑)」。

本モデルは1985年、モデル名の頭文字に“V”を冠する“Vシリーズ”の一作として誕生。軽量性に特化した「AIR VENGEANCE」、秀でた安定性を誇る「AIR VENTURE」とともに、優れたクッショニングで当時のランニングシーンに一石を投じたといわれている。こちらはオリジンではなく復刻版。ナイキ自体は多数派だが、ユーロ圏は話が別として、この令和の世に80年代生まれのレトランモデルを選ぶなぞ少数派もいいところ。だが彼にとっては、ファッションではなく、あくまでデイリーユースだという。
「自分の中で“どうでもいいクツ認定”のラインというのがあります。これも5年間以上愛用し、汚れているし、完全にそっち側。その分、足にも馴染んでいるので撮影にも海外出張にも履いていきます。CMの現場は生モノで何が起こるか予測不可能。ルーティーンを決めすぎると、それが自分のストレスになることも。そんな中でも、これさえ履いていれば間違いないという安心感ですね」と愛着満点のご様子。

「本来の自分は、“こういった場面なら、絶対にこのスタイルでなければいけない”と、マイルールにがんじ絡めになるタイプでしたが、この14年間でフレキシブルに対応できるよう変わりました。たとえば、その日のクライアント、出演者などに合わせた格好をしていく。すると服をイジってもらってコミュニケーションのキッカケになったりもするんです。もう1色、ブラウンスウェードのタイプも持っていて、そちらも現場スタッフから好反応をよくいただきますね」。

とはいえ、やはりコダワリは強い。この日の装いは、水泳経験者ということでスイミングモチーフの古着のロンTに、学生時代にバイトをしていたこともある無印良品のチノパン、頭には小学生時代、家族旅行にて訪れたアメリカで購入した、映画『バットマン・フォーエヴァー』のキャップ。アイテム選びにおいて“理由”をいかに重要視しているかがよく分かる。
「ついつい作品の登場人物の感覚で設定を考えてしまう。これは多分、映像ディレクターの本能なんでしょうね。古着屋で気になったモノを見つけても、メーカーや素材、生産国といった製造背景にいたるまでメッチャ調べますし。もちろんデザインは大事ですけど、それ以上に自分は“ロジック”で生きている人間だと思います」。へそ曲がりなスニーカー選びも、情報量多めで天邪鬼な映像ディレクター・畔柳恵輔というキャラビルドの一環であると考えれば納得がゆく。

「最近は、それも自分のキャラだからイイじゃんって思うようになりました。僕のことを、『変わっていますよね』とかいっている代理店やクリエイター陣に、『あなたが知っている俺なんて、氷山の一角でしかないからな!』 なんて、心の底でほくそ笑みながら」。そう言ってニヤリと不敵で素敵な笑みをこぼす。
* * *
これから先、このスニーカーを履いて、どんな人間と出会い、どんな現場に入って、どんな仕事をするのか。そう考えるだけでワクワクすると楽しげに話す畔柳さん。1コマ先でさえ何が起こるか分からない映像業界を、しっかり両足でエアのクッショニングを感じながら、彼は走り続けていくに違いない。これからもずっと、きっと。
>> スニーカーとヒト。
<取材・文/TOMMY>
 TOMMY|メンズファッション誌を中心に、ファッションやアイドル、ホビーなどの記事を執筆するライター/編集者。プライベートでは漫画、アニメ、特撮、オカルト、ストリート&駄カルチャー全般を愛する。Twitter
TOMMY|メンズファッション誌を中心に、ファッションやアイドル、ホビーなどの記事を執筆するライター/編集者。プライベートでは漫画、アニメ、特撮、オカルト、ストリート&駄カルチャー全般を愛する。Twitter
【関連記事】
◆スピングルムーヴがMIKASAとコラボ!だから素材はサッカーボールと同じなんです!
◆オークリーはサングラスだけにあらず。2000年代に爆発的にヒットしたシューズが復刻!
◆オン「クラウド X 3」ならランニングからワークアウトまでOK!
- 1
- 2