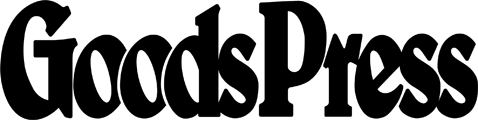中山 雅(なかやま・まさし) 1965年、広島県生まれ。1989年にマツダへ入社し、2011年からロードスターのチーフデザイナーを担当。その手腕が世界的に高く評価され、ND型は2016年『ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー』と『ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー』をダブル受賞することに。2016年7月には、商品本部主査 兼 デザイン本部チーフデザイナー ロードスター担当に就任。“ロードスター愛”は深く、自宅ガレージには最新のND型と、26年間所有し続ける初代NA型が仲良く並ぶ。
クルマのエンジニアリングとデザインは一体であるべき
——『ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー』と『ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー』のダブル受賞について、中山さんはNDのどんなところが高い評価につながったとお考えですか?
中山:『ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー』に限った話ではありませんが、クルマの世界的な賞レースでは、クルマ全体を評価する賞のほかに、たいてい、デザインだけを評価する賞があるんです。いい換えれば、“エンジニアリング賞”と“スタイリング賞”という、ふたつの賞が存在する感じでしょうか。
でも、それによって「Aというクルマはカッコいいけれど中身がイマイチ」、「Bという車種はカッコ悪いけれど中身がいい」といった具合に、クルマの“中身”と“外見”が別々に評価されているかのような印象を人々に与えてしまいます。
本来は、それじゃいけないと思うんです。ロードスターを手掛けている我々としては、そんな状況に対し、正直、納得いかないものがありました。
ロードスターというクルマを説明する時、我々はいつも、クルマの中身から説明します。「こういうレイアウトがあって、ムダなくモノを作って、そのためにデザイナーもいっしょになって頑張った…」といった具合に。ロードスターは既存のシャーシの上に、単にパカッとカバーを被せただけのクルマではありませんから。
ところが、賞が分かれてしまうと、本来は一体であるべきクルマのエンジニアリングとデザインが、別々の要素に思われてしまう。現代のクルマ開発において、デザインだけを切り離して評価するのは、ナンセンスなんです。
しかし今回、NDが『ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー』と『ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー』をダブル受賞したことで、クルマのエンジニアリングとデザインは一体であるということが、改めて認識されたと思っています。双方獲得したことによって、カーデザインの本来あるべき姿を世界に示せたのではないか、と。それだけに、今回のダブル受賞は、本当に意味があったと思いますね。

左から、2016年のワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー、ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー、そして、2015-2016 日本カー・オブ・ザ・イヤーの受賞トロフィー
——デザインというワードを、我々はしばしば、簡単に片付けてしまいがちですよね。デザインとは本来“意匠”という意味のほかに“設計する”という意味も含んでいる言葉。なのに、例えば“デザイン家電”など、どちらかといえばスタイリング重視のニュアンスで使い、また、そう捉えてしまっています。
中山:本来、デザインって建築に近いものだと思うんですよ。建築は、構造を考える人とデザイナーとが一体になって成立している。カーデザインも、本来そうあるべきなんです。
——そんなNDロードスターのカッコいい部分を言語化していただくとしたら、どんな言葉になりますか?
中山:クルマの開発だけでなく、物事全般にいえることですが、最も塩梅がいいところ、つまり“ちょうどいいところ”を見つけ出すという作業が、実はとても難しいんです。なれるかどうかは別として、一番を目指すというのは意外と簡単。でもロードスターというクルマは、その“ちょうどいいところ”を見つけ出さなきゃいけないクルマであり、しかも、そこに居続けなければならないクルマでもあるんです。
とはいえ、時代や周りは変化しますから、“ちょうどいいところ”にとどまり続けるのは簡単ではありません。周りのクルマを見渡せば、どんどん速くなっているし、重くなったからといってさらにパワーを上げるモデルも存在する。そういう世の中なのに、ロードスターだけは“ちょうどいいところ”に居続けようとする。これって勇気が必要なんですよ。でも、守り続けることで、もしかしたらロードスターは、クルマの中軸になるかもしれない。「ここがクルマの中心ですよ」という水準器のような存在に。我々はそれを、絶対に守らなければいけないと考えています。

よく食べ物に例えるんですが、甘いとか辛いとかっていう味覚は、大人になってからでも経験などによって変化する、相対的な評価です。でも、美味しいとかマズイという基準は、生まれた時にはすでに頭の中にプリインストールされている、決してブレない評価。
ロードスターはそれと同じような存在だと思っていて、乗り比べてみてこっちがパワフルだとか、あっちが速いとかっていう具合に評価されるクルマではないんです。食べてみたら美味しい。乗った瞬間に美味しい。そういうクルマがロードスターだと思っています。
なので、NDのデザインは、ただ美味しいと感じられるものにしたいと考えました。NDはNAと同じ香りがすると思いますが、でも、単にレシピを再現したものではないんです。
——実際のデザイン作業は、苦労の連続だったと想像します。今あらためて振り返ってみて、いかがでしたか?
中山:終わってみたら、案外やりやすかったな、というのが本音です。NDのプラットホームはブランニューで立ち上げたもの。なので、あれやこれやといった前提が少なかった。NBやNCに比べると、フリーハンドでやれた感じがありますね。
先代のNCは、ひとクラス大きな4ドアスポーツ「RX-8」のプラットホームをベースにしていたので“ちょうどいいところ”を目指すのが大変だったんだろうな、と想像します。

——なるほど。前提が少ない分、制約も少なかった、というわけですね。
中山:NDは搭載するエンジンも小さい。1.5リッターです。だから、いろんなところをいい意味で“華奢”に作れる。必要以上に強く、硬く作る必要はない。だから、デザイナーサイドからいろいろな要求をしても、エンジニアが実現できた部分が多かったと思います。
あえてデザイン面で難しかった要素を挙げるとするならば、それはやはり「3世代続いてきた暖簾をいかに守るか?」ということでしょうね。
本音をいうと、やっぱり恐かったですよ。社内の上司やエンジニアたち、そして、これまでロードスターに携わってこられた諸先輩方も、もちろん恐かったですが、やはり一番恐かったのは、歴代ロードスターのオーナーの方々ですね。皆さんの期待を裏切ったら大変な目に遭いますから。皆さんの期待に応えなければいけない、それが一番難しかったことですね。
——そういうプレッシャーの中、NDを成功に導くことができた要因は、なんだったとお考えですか?
中山:マツダ社内で、デザインに対する理解が深まっていること、ですかね。特に2012年にデビューした「CX-5」以降、デザイン・ブランドスタイル担当役員の前田育男が率先し、デザインをマツダの武器のひとつにしようと努力してきました。
そして今、マツダブランドの重要な武器のうちの1番目か2番目くらいに、デザインを位置づけてくれている。会社がそう決めてくれたので、皆のサポートがすごく強力でした。だから、やりやすかったんだと思います。思いっきり仕事ができました。
——そういった社内の理解やサポート体制が、『ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー』と『ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー』のダブル受賞につながった、というわけですね。
中山:そう思います。実は「ロードスターだから」とか「エンジニアとデザイナーが頑張ったから」というよりも、今のマツダだから受賞できたものではないかと思っています。(Part.2へ続く)
(文/ブンタ、写真/グラブ、田中一矢)
<関連記事>
ロードスターの真実・マツダ 中山 雅(2)入らないならあえて残す。逆転の発想が生んだRFのルーフ
吉田由美の眼★マツダのZoom-Zoomな香水、Soul of Motionを体験
本邦初公開!マツダ「ロードスター RF」に2000人超のファンが熱視線
- 1
- 2