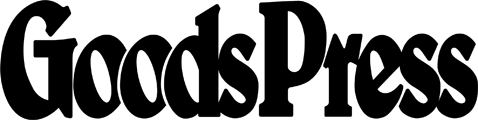右)大竹 実 1954年、群馬県生まれ。大学院では機械工学を専攻。1980年、富士重工業に入社。技術本部にてレオーネ、サンバーのサスペンション設計を担当後、アメリカにて技術調査や研究に従事。帰国後、フォレスターやインプレッサなどの開発プロジェクトに参加。2009年、富士テクノサービス取締役を経て、現在は常勤顧問に。埼玉工業大学特任教授。週末はアマチュアオーケストラにてトランペット演奏を楽しむ。左)芝波田 直樹 1960年、長野県生まれ。信州大学工学部卒業後、富士重工業入社。車両研究実験部にて操縦性や安定性、乗り心地の研究実験開発業務などを担当。その後、米国におけるスバル車の研究開発を経て、2016年より富士テクノサービス車両研究実験室主管に。テニスやフライフィッシングなどを楽しむアウトドアスポーツ派。
「私が入社した頃は、2世代目『レオーネ』のデビュー直後でしたから、現場にはまだまだ、最初の4輪駆動の試作車『ff-1 1300Gバン』の開発に携わった方が多くいらっしゃいました。ですから少なからず、開発の苦労話を聞く機会もありましたね(笑)」
そう語るのは、現在、スバル車の技術開発を手掛けるグループ会社・富士テクノサービスで顧問を務められている大竹 実さん。1980年に富士重工業に入社した大竹さんは、レオーネや「サンバー」などのサスペンション設計、スバル各車のシャーシ設計などを手掛けてきた生粋のエンジニア。そして現在は、スバルの社員を対象に開かれる歴史講座の講師も務められる、スバル車の歴史にとても精通されたおひとりです。
「このff-1試作車で培ったノウハウは、後のモデルに大きな影響を与えました。スバルのクルマづくりにも大きな影響を与えたクルマです」
そのように続ける芝波田 直樹さんも、元は富士重工業で腕を鳴らし、現在は富士テクノサービスの車両研究実験室において、スバル車の戦略企画に携わるエンジニア。
そもそも、当時の富士重工業は、なぜ4輪駆動車の開発に着手することになったのでしょうか? 実は「東北電力から自動車メーカー各社へ打診があった」と大竹さんは振り返ります。
「1960年代後半のことです。当時、東北電力では雪深い山間部の送電線点検に、ジープなどのミリタリー系4WD車を使っていましたが、何しろ乗り心地が悪く、ヒーターも効かなかった。そこで、自動車メーカー各社に走破力と快適性を兼備した、乗用車ベースの4WD車開発を打診したそうです。とはいえ、そういったクルマに対して市場ニーズがあるのかどうか、全く分からない時代でしたから、受けてくれるところはなかったそうです。
もちろん、富士重工業にも依頼があったのですが、当時はスバル『360』の後継となる『R2』の開発で手いっぱい、という状況。そこで東北電力は、地元の販売会社である宮城スバルに対し「こういった4輪駆動車を作れないか?」と、1970年の春頃に相談したそうです。そうしてまずは、宮城スバルで試作車の製作がスタートしたのですが、図面も何もない状態で、現物合わせで作るというのは、さぞかし大変なことだったと思います」
ベース車として選ばれたのは、当時の富士重工業で唯一の乗用車であり、当時としては画期的な前輪駆動レイアウトを採用したスバル『1000』。その商用車であるバン仕様に、マイナーチェンジ版であるff-1用の1100ccエンジンを搭載した車両が用いられましたが、開発作業はかなり難航したのこと。

スバル1000は前輪駆動ゆえ、新たに後輪を駆動するためのメカニズムが必要となりますが、縦置きの水平対向エンジンと、その後ろにトランスミッションがあることから、4輪駆動化は容易だと思われていたみたいですが、そう単純な話ではなかったそうです。
「その頃、後輪用として使えそうな、4輪独立式サスペンションを備えた駆動系を搭載していたのは、日産の『ブルーバード』と『グロリア』、それと、いすゞの『ベレット』くらいでした。そこで開発陣は、ブルーバード用のものを選んだらしいのですが、実は最初にチョイスしたのは、タクシー用だったそうです。すると、前後のディファレンシャルにおけるギヤ比が違いすぎて、クルマが“ウサギ飛び”しているかのように跳ねた、なんて話も聞きました(苦笑)。結果的に、その後試した一般車用のデフのギヤ比がほぼ同じだったので上手くいきましたが、当時は『コレでだめなら諦めるしかない…』という状況だったらしいです」(大竹さん)

こうして、宮城スバルの手によるff-1ベースの4輪駆動試作車が完成したのは、開発を始めてからわずか10カ月後の、1970年暮れのこと。翌71年2月には、豪雪地として知られる山形県の月山をはじめ、スキー場などで試験を繰り返し、ジープなどとの比較なども行われたといいます。
「4輪駆動車としての性能はもちろん、快適性への評価もとても高かったんです。この試作車はその後、富士重工業へ持ち込まれると、開発拠点がある群馬と東京・三鷹のエンジニアによる打ち合わせが行われ、すぐに本格的な設計・開発がスタートしました。この時ベース車として選んだのは、ff-1 1300Gシリーズのバンでした」(大竹さん)
こうして4輪駆動車の開発が富士重工業本体へと移管されたことで、一気に量産へ! となったかといえば、そう事は上手く運びませんでした。
「後に登場するレオーネが、乗用タイプとしては初の量産4輪駆動車になりました。当時は4WD車の需要なんて、さほどないと思っていたのでしょう。ですから、まさかレオーネの販売台数の3割弱を4WD仕様が占めるなんて、夢にも思っていなかったと思います(苦笑)」(芝波田さん)

実際、当時の企画会議の資料を検証した大竹さんによると、4輪駆動車開発への苦悩が、具体的に分かる数字がいくつか見つかったそうです。
「量産に向けての収益の計算では、年間500台、同1000台、同3000台と、3つのケースで検討が行われたようですが、その差はなんと6倍。こうした数字からも分かるとおり、富士重工業では一般の方からのニーズがどれくらいあるのか、当時は全く読めていなかったんだな、と思いました」(大竹さん)
ともあれ、市販化に向かってようやく動き出した、乗用車型としては初の4輪駆動車。大竹さんによると、当時のエンジニアたちには、ちょっと“苦笑い”してしまうような、技術屋ならではの葛藤もあったそうです。
「スバル車の歴史を振り返ると、初の乗用車として開発された、スバル『1500(P-1)』と呼ばれる試作車から、初の量産小型車となったスバル1000までの間に、実はふたつの試作車が存在します。
ひとつは『A-5』という1500ccクラスの試作車で、これは水平対向4気筒エンジンや前輪駆動など、後のスバル車へと継承される特徴を備えたクルマでした。しかし、前輪駆動に欠かせない“等速ジョイント”が開発途上で、振動がひどかったそうです。その後、A-5の流れをくむ『A-4』という1000ccクラスの小型車の開発がスタートします。このA-4では、等速ジョイントの開発にも成功していますし、安全性や居住性もライバルの先をゆくものでした。これが後に、スバル1000として結実するのですが、4輪駆動車の開発には、スバル1000の当初のコンセプトと相反する部分がいくつかあったのです…」(大竹さん)
スバル1000開発の陣頭指揮を執ったのは、スバル360やサンバーの生みの親として知られる百瀬晋六氏。百瀬氏がスバル1000の開発に当たって特に重視したのは“居住性”と“操縦安定性”だったといいます。
「スバル1000は国産車として初の前輪駆動車ということで、誕生までには相当な苦労があったようです。前輪駆動車の特徴として居住性の高さが挙げられますが、スバル1000は、後輪駆動車ではプロペラシャフトをとおすために必要な“センタートンネル”という車体中央の盛り上がりを完全になくし、フラットな床面を実現したのです。さらに、水平対向エンジンなので、シリンダーから伸びる排気管が右バンク用、左バンク用と独立していますが、これを車体左右の“サイドシル”(ドアの下に位置する敷居部分)に沿わせるなど、細かい工夫が施されていました。

また、高速道路が開通した頃に誕生したクルマですから、スバル1000は操縦安定性にもこだわっていました。等速ジョイントの開発はもちろんですが、4輪独立式のサスペンションやインボード式ブレーキなども採用しています。こうした先進のメカニズムや優れた操縦性については、ドイツ車などのヨーロッパ車を熱心に研究し、実用化にこぎ着けたそうです」(大竹さん)
こうして誕生したスバル1000ですが、4輪駆動車となると、どうしても車体中央にプロペラシャフトが貫通させる必要があったのです。
「サイドシルに排気管をとおす。しかも左右とも、となると、コストは2倍掛かるわけです。そこまで苦心して作り上げたフラットフロアなのに、その案を破棄してまで4輪駆動車を開発する…。『せっかく苦労してセンタートンネルをなくしたのに…』と、当時のエンジニアたちは大いに葛藤したようです」(大竹さん)
とはいえ、富士重工業本体へと開発の主導権が引き継がれたことで、実用化や量産化に向けての技術開発が加速していったのも事実。一方で“改造して”作った試作車ではなく、量産を前提とした試作車となると、法規的な問題をクリアする必要も出てきます。
「フロアを再設計するわけにはいきませんから、プロペラシャフトは室内を貫通させ、その上にカバーを装着しました。貫通部にもゴミや異物が入り込まないよう“たわし”のようなシールを作りました。また、宮城スバルの試作車では、燃料タンクを室内に積んでいましたが、これも左右に振り分ける、鞍のような形状に変更しています。今なら燃料はポンプで吸い上げるので、タンク形状にもある程度の自由度がありますが、当時はそんな装置はありませんでしたので、形状を工夫し、ゴムホースで連結して…といった具合に、創意工夫で課題をクリアしていきました。

そして、4輪駆動車に欠かせないリアのディファレンシャルギヤケースを車体に装着するには、車高を数十ミリ上げる必要がありました。これにより、室内空間の配置もわずかではありますが、変更が必要となります。すると法規上、貨物バンに必要とされる荷室スペースの要件を満たせない。そこで、東北電力に掛け合ってリアシートを前にズラす許可を得て、スペースを稼ぎ出しています。こうして製品としてカタチにはなりましたが、開発期間はわずか半年。これはまさに、異例中の異例だと思います」(大竹さん)

開発が急がれた理由のひとつは、モーターショーの存在。なんと、宮城スバル向け試作車の完成から1年も経たない1971年東京モーターショーの会場に、スバル「1300Gバン4WD」の試作車が展示されたのです。


縦置きされた水平対向エンジンと、その後ろに配置されるトランスミッション、そこから伸びるプロペラシャフトとリアデフ。今日に受け継がれるスバルの“シンメトリカルAWD”の偉大なる源流が、初めて人々の目に触れることになったのです。
「このクルマ以降も、スバルはレオーネや『レガシィ』などに、20年以上にわたって日産からリアデフとプロペラシャフトを供給してもらっていました。もしあの時、ブルーバード用のリアデフとプロペラシャフトがなかったら、今のスバルAWD車はなかったかもしれませんね(苦笑)」(芝波田さん)

芝波田さんはそういって笑いますが、一方では、自社製ではないことに起因する苦労が、少なからずあったようです。
「ff-1ベースの試作車に使用したブルーバード用のデフは、図面が手元になかったので、現物を採寸して車体を加工したそうです。また、継続的に供給してもらうようになっても、日産に対してギヤ比の仕様変更まではお願いできないので、以降のクルマでは、リアデフから逆算して前側デフのギヤ比を決定した、なんてこともありました。もちろん現在は、自社製デフを採用しています(笑)」(大竹さん)