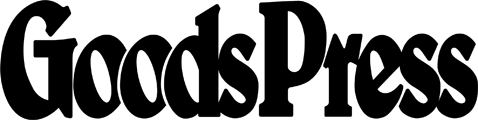ライカの歴史の始まりは、およそ100年前の1914年のこと。ドイツのウェッツラーという坂の多い小さな町にライツ社があって、そこにオスカー・バルナックという技術者がいた。
彼は体が弱かったらしく、当時の重く大きなカメラを持って坂を登ることにうんざりしていた。
その頃は写真と同じサイズのフィルムが必要だったためカメラは巨大で、フィルムの感度も低かったため撮影には三脚が欠かせず、ちょっとした旅行に出るくらいの荷物だっただろう。
そこで金属製のパイプを潰した小型なカメラの製造を思いつく。
映画用のフィルムを2コマつなげて撮影して、その小さなフィルムから引き伸ばし機を使って大きなプリントをするシステムを実現するためのカメラを2台だけ試作した。
これが後に「ウルライカ」と名づけられる。
この後に作られた「0型ライカ」と呼ばれる試作品が、2012年に216万ユーロで落札されてニュースになったことでもわかるように、写真の歴史のなかでも画期的なことだった。
だがこの小型カメラのアイディアは十年ほどお蔵入りになっていた。時代が変わり、小さなカメラの需要を感じたライツ社は、これを製品化することを決断する。
ライツのカメラということでライカと名付けられ、バルナックの名前をとって初期のライカをバルナックライカと呼ぶようになった。

ライカが本格的に世界を代表するカメラとなっていくのは、グラフジャーナリズムの繁栄との熱い関係があってこそだった。
その機械としての性能を、実際に撮った写真が証明していったのだ。
人々は新しい世界を見たがり、それを伝えるのが写真とグラフ雑誌の役割だった。報道写真家が世界を飛び回り、彼らのカメラバッグには、小さく丈夫で画質のいいライカが欠かせないものとなった。
歴史的瞬間をライカが見つめてきたと言っていい。
1954年に、現在のライカの原型ともなっているM型の最初のモデルであるライカM3が発売される。フィルム交換が確実でスピーディーに、ピント合わせとフレーミングが別々の窓だったのがひとつに、巻き上げがノブからレバーに変わった。
道具の進化がほとんどそうであるように、便利で扱いやすくなった。ここから1967年に発売されたライカM4までが“ヴィンテージ”と呼んでいいライカだろう。
『ライ麦畑でつかまえて』の著者であるサリンジャーの短編『テディ』のなかにこんなセリフがある。
「カメラを持たせただと!」と、言った。「あれはライカだぞ、俺の!」
(「ナイン・ストーリーズ」著:J・D・サリンジャー 訳:野崎孝)
この短編集の発行が1953年だから、サリンジャーはまだM型ライカが世界を席巻することを知らない。それでもこうして小説に名前を書けたということは、ライカがすでに高級カメラの代名詞として知られていたことを示している。
小説でいえば、007シリーズのイアン・フレミングは趣向品へのこだわりが強く文中にウンチクが多いことで知られているが、ジェームズ・ボンドがM3を持っている記述があった。
スパイが使うならもっと小型のカメラだってあったのに、美しさと品格にこだわるジェームズ・ボンドらしい選択だ。
ライカはデザインが美しいため映画に登場することも多く、プライベートでも愛用してるブラッド・ピットの「スパイゲーム」や、最近ではウッディ・アレン監督の「それでも恋するバルセロナ」でスカーレット・ヨハンソンが手にしていた場面が印象に残っている。
世界一の写真家と言っても過言ではない、フランスのアンリ・カルティエ=ブレッソンは、ライカとの出会いにより写真活動を始めて、ほとんどの作品をライカと50mmレンズで撮り、その生涯を終えた。
これらはライカが高級であるだけでなく、名実ともに世界最高のカメラである証だろう。

その後、日本のメーカーによる一眼レフの逆襲にあう。レンジファインダーシステムは利点が多いものの時代遅れとなり、過去の遺物となったかに見えた。
ところが便利な時代になるほど、手間がかかることを慈しむ人たちが必ずいる。面倒さは喜びと紙一重のところにあり、楽しさが感じられるプロセスが豊富にあるということでもあるのだ。
誰にでも手に入るものではないほうが、所有している喜びも感じられる。街を歩いていて「それライカですか?」と声をかけてくる人は世界中にいた。こんなことライカ以外ではほとんどない。
2006年にデジタル化されたライカM8が発売された。デザインとサイズをほとんど変えずに作ったことにライカのプライドを感じた。現代ではフルサイズと呼ばれている24mm×36mmのフォーマットはライカ判と呼ばれる。
ライカの歴史とはただの高級カメラの物語ではなく、小型カメラの歴史であり、写真の黄金期の歴史と言っても過言ではないだろう。
(文・写真/内田ユキオ)
【短期連載】写真には物語があるはコチラ
- 1
- 2