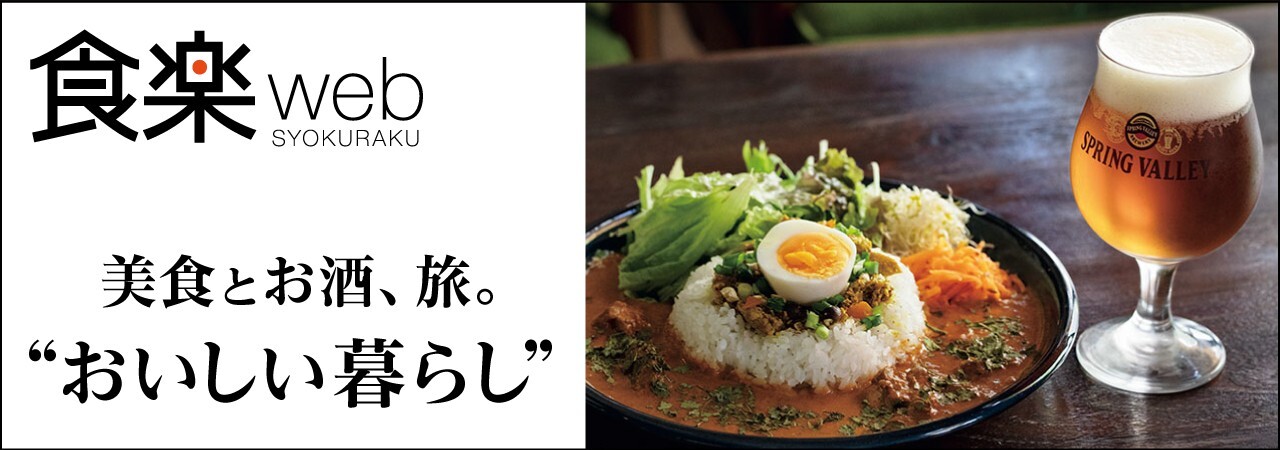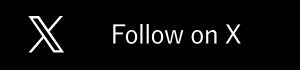■一筋縄ではいかなくて…
ご機嫌最高!のモノグラムではありますが、そこはそれ、60年以上前のプラモデルです。現代のキットのようなワケにはいきません。
主翼や胴体といったパーツのあちこちにヒケ(パーツの表面がエクボ状にへこんでいる状態)や突き出しピン(金型から押し出す際にパーツに残る丸い跡)等が目立つので、修正が必要です。
当時のプラモデルは盛る、削るといった作業は当たり前でしたらから、粛々と盛って、削って修正します。機体を仮組みしてみると、う~ん機首がちょっと短いようですが…古き良きご機嫌最高!モノグラムの味(笑)、ということでストレートに製作を進めます。

▲水平尾翼の裏の目立つ突き出しピンの跡とコピーライトの刻印が目立つので削って修正。そう言えばモノグラムのキットはかなり後年のキットまで水平尾翼裏にコピーライトの刻印が入っていた

▲塗装して組み上げた計器盤。操縦桿のハンドルは実機もプラスチックなので、塗装せずそのまま組んでいる

▲トライペイサーPA22は前脚式なので、完成後尻もちをつかないように、機首に釣り用のおもり(板鉛)を15グラム詰め込んだ
■エンジンだって再現されてます
キットはエンジンカウルが取り外せるようになっており、内部には(当時としては)精密な水平対向4気筒のライカミングO-125 エンジンンが収まっております。ちゃんとシリンダーのフィンまでモールドされているので、銀でエンジン本体を塗装したのち、タミヤのスミ入れ塗料(ブラック)を流し込んでディテールを強調してやるだけで結構良い感じに仕上がりました。

▲2個のパーツで再現された290馬力のライカミングO-125 エンジン

▲ディテールがしっかりしているので、シルバーで塗装してスミ入れをしただけでもかなり雰囲気のある仕上がりに
■機体の塗装
入手したキットはインスト(説明書)が欠品だったので、塗装はボックスアートを参考に、それらしくカラーをチョイス。民間機ですから自由なセンスで塗装してもいいですしね。
機体は60年代を意識して淡いクリーム色を調色して、それをベースに赤でグラフィックを入れてみました。赤が鮮やかすぎるので、もう少し暗くても良いかもしれません(再塗装考え中)。

▲まずは機体各パーツをホワイトサーフェイサーで下地塗装

▲機体の基本色としたライトベージュはMr.カラーのホワイト+イエローで調色したものを使用

▲上が自作したライトベージュで塗装した主翼。下はホワイトサフの状態。わずかな色の違いで雰囲気が大きく変わるのが分かる

▲ライトベージュの基本塗装が終わった機体各パーツ。このあと赤を重ねるので、しっかりと乾燥させる

▲マスキングをしてタミヤラッカー塗料のブライトレッドを塗装

▲主翼には1950年代テイストでラインを入れてみたが、鮮やかすぎて、思っていたイメージとちょっと違ってしまった。もう少し赤の彩度をおとした色で塗り直した方が良さそうだ
■見よ!このディテール

▲出番待ちのハンターのおふたり(笑)
キットに付属するハンターのふたりですが、パーティングラインや突き出しピン跡を丁重に処理してサーフェイサーで下地塗装してみると、獲物を仕留めて笑顔を浮かべるハンターの顔のディテールや服のシワの再現等の細かさに驚かされました。現代のフィギュア並みとは言いませんが60年以上前のフィギュアなんですよ、やっぱり凄い。ご機嫌最高!モノグラムの面目躍如といったところです。

▲サフ拭きした状態のハンター。このフィギュアの味のある雰囲気がモノグラム最高!と思わせてくれる
■時に流れには勝てませんでした…
民間登録の機体番号が大判のデカールで再現されていますが、さすがに劣化が激しくフィルム自体も黄変しており、水に浸けてもフィルムが台紙から剥がれない状態でした(要するに使えない)。これは機体番号を手描きするか、代替えデカールを探すかないようです。
ちなみにプラモデルを作らずにため込むと、どんなキットでもまずデカールが劣化していきます。黄変や色抜け、湿気が多いとカビが生えることもあります。なのでプラモデルは積み上げないでどんどん作るのがよろしいかと(経験談)。

▲劣化したデカール。水に漬けても台紙から剥がれなかった(泣)
次回は機体の仕上げと雰囲気満点のフィギュアの塗装です。お楽しみに!
>> [連載]達人のプラモ術
<製作・写真・文/長谷川迷人>
【関連記事】
◆戦う建機!? イスラエルの魔改造車輌「装甲ブルドーザーD9R」を製作【達人のプラモ術<D9R装甲ブルドーザー >】
◆映画にもなった宇宙船「アポロ13号」の破損状態を製作!【達人のプラモ術<アポロ13号>】
◆カーモデル製作はボディの塗装から!【達人のプラモ術<NISSAN フェアレディ 240ZG>】
- 1
- 2