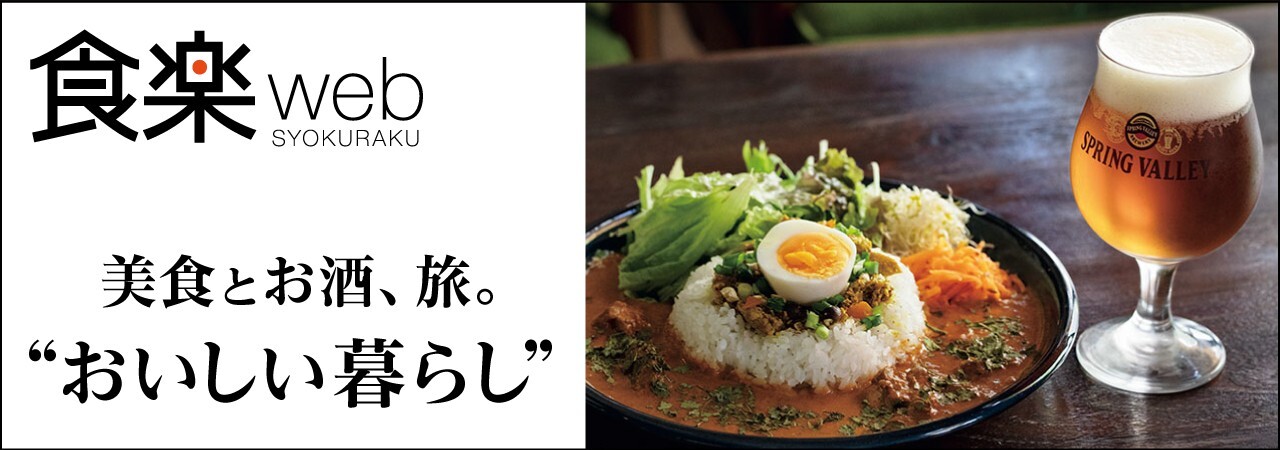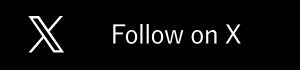コーヒーを科学した「BLOSSOM ONE BREWER」98万円(税別)
この「BLOSSOM ONE BREWER」の最大の特徴が、コーヒーの抽出を、徹底的に科学したことにある。CEOのジェレミー・クエンペルは、MITの卒業論文に「コーヒーメーカー論」を書き上げたというコーヒー好きだ。
彼が着目したのが、コーヒーの味や香りを左右するのが、抽出時の豆の温度であるということ。そこで理想の味を追求するために、徹底した温度管理を追求。ボイラーだけでなく抽出ユニットにもリング状のヒーターを配置することで、0.5℃単位で抽出温度を調整できるドリップコーヒーマシンを生み出したのだ。

タンクに入れた水はボイラーで温められ、前面にある抽出ユニットに適量が抽出される。湯温は2つのヒーターとPID制御で素早くコントロールされる

湯温や量、蒸らし時間などをレシピとして登録できる
設定できる抽出時の温度は50~95℃。豆に合った最適な温度が設定できる。しかし、それでいてすべてが機械任せの全自動というわけではなく、豆の量やかき混ぜるタイミングなど、あえて手作業も多く残している。
本体には抽出温度や蒸らし時間などレシピとして登録することが可能。それらのレシピを選ぶと、設定した温度や時間になったらアラームを鳴らしてくれる。
あとは、そのレシピに従うだけのシンプルな操作で、美味しいコーヒーを淹れられるというわけ。厳密に管理されていながらもどこかひとが淹れた温かみも同時に感じることができるのだ。
「BLOSSOM ONE BREWER」でコーヒーを抽出してみた
ここからは写真で「BLOSSOM ONE BREWER」でのコーヒー抽出ステップを見ていこう。

1.まずは本体後方にあるタンクに水を入れる

2.ステンレスフィルターにペーパーフィルターをセットして本体に取り付ける。ステンレスフィルターのみでも抽出可能

3.ダイヤルを回してレシピをセット。レシピは最大200種類設定できる

4.抽出ユニットに適量のコーヒー豆をセット

5.スイッチを入れてコーヒーの抽出をスタートする

6.アラートに従って抽出ユニット内のコーヒー豆とお湯を攪拌する

7.アラートに従い、抽出口のレバーをオープンにして、抽出をスタート

8.レバーを倒して、最後までしっかりと抽出する
すっきりとした飲み口でコーヒー豆の味の繊細な味が楽しめる
このとき、数種類のコーヒー豆を用意して、それぞれ飲み比べさせてもらった。面白かったのが、普段筆者が飲み慣れているいつものコーヒー豆。食料品雑貨チェーンでいつも買っている、それほど高くないモカブレンドだ。

「BLOSSOM ONE BREWER」で普段飲みのコーヒーを抽出。香りがすでに違う
ひと口飲むだけで、いつもコーヒーメーカーで淹れている味との違いを感じた。さっぱりしていて、酸味がさっと現れて消えていく。普段は酸味をそれほど感じていなかったので、「BLOSSOM ONE BREWER」でしっかりと蒸らし、抽出した結果、そのポテンシャルが引き出せたようだ。

ひと口飲んで、あれ?ほんとにこれいつもの?とちょっと確認。それほどに味の輪郭がしっかりとして、酸味やコク、苦みが堪能できた
その他、用意していただいた豆を異なる抽出温度で淹れて飲み比べて見たが、抽出する温度によってしっかりとしたコクが味わえたり、さっぱりしたりと、その違いが楽しめることに驚いた。
「BLOSSOM ONE BREWER」はこのように繊細な設定ができるものの、レシピは本体に記録され、蒸らし時間や混ぜるタイミングなどをアラームで教えてくれるため、誰が淹れても美味しく淹れることができるという。人の手の温かさはあるが、淹れる人物の技術に依存しないのだ。
アメリカのIT×日本のモノづくりで実現!
世界トップクラスに優秀なふたりのエンジニアが作った注目のコーヒーメーカー「BLOSSOM ONE BREWER」。
この製品の開発にはもうひとつの物語がある。この「BLOSSOM ONE BREWER」はギヤモーターのパイオニアとして実績がある日本の企業、ツカサ電工が製造を手がけているのだ。
つまり信頼の日本製。開発を行ったふたりのエンジニアとの信頼関係が「BLOSSOM ONE BREWER」の量産を実現したのだ。

徹底した温度管理機能を搭載したコーヒーメーカーは日本の技術によって量産化される
「BLOSSOM ONE BREWER」は税別98万円と決して安くはない。しかし、担当者によると、決して「業務用」だとは思っていないという。
すでに一部のCafé & Meal MUJIで導入はスタートしており、それらのお店を訪ねることで、「BLOSSOM ONE BREWER」で抽出したコーヒーが堪能できる。真面目にカフェをオープンしたいと考えている人、趣味でコーヒーを突き詰めたいという人ならば、自宅に置くことを検討してみてもいいかもしれない。
(文/コヤマタカヒロ)
- 1
- 2